「合理的配慮」って知っていますか?
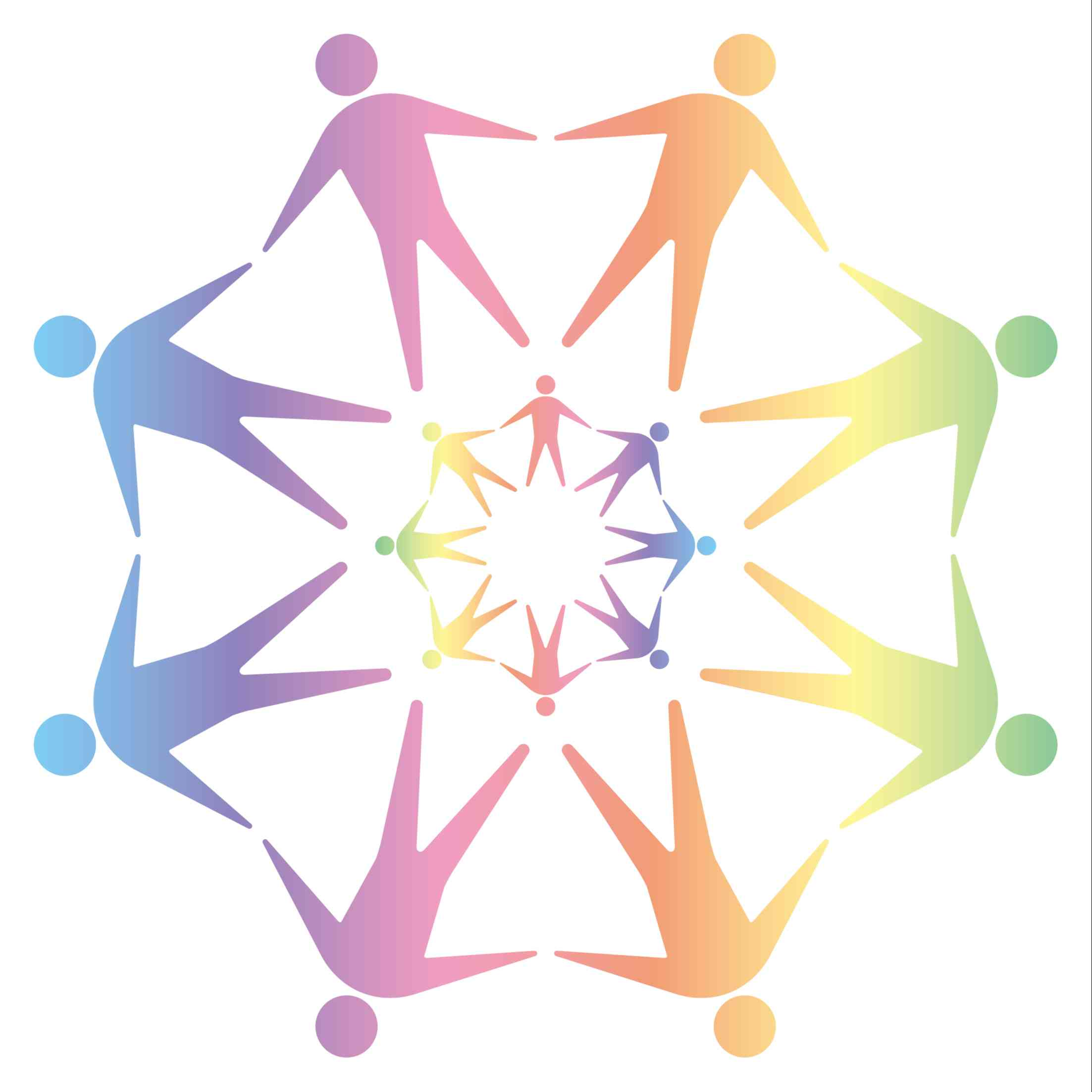
私が勤めている会社は、障がいのある人とない人が共に働く「共生企業」です。
さて世間では、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。ということで、今回は私が考えている合理的配慮について話していきたいと思います。
私自身は健常者で、この会社に入社して3年目となりますが、障がいをお持ちの方にどう配慮しているか?と自問したところ、私自身障がいのある方に対して特別な配慮をしているわけではありません。(もちろん配慮依頼がありましたら、対応しています。)
私見として「健常者と障がい者」という区別をしないように考えています。「障がいを持っているから」「障がいを持っていないから」ではなく、「一緒に働いている人」という視点で人と接しています。このように捉えると、みなさん日常の何気ない関わりの中でも、「障がいがあるから配慮をしている」ことはなく、障がいの有無に関係なく自然と配慮を行っているのではないでしょうか。
みなさん、配慮という言葉をどのように捉えるでしょうか?
「配慮」という言葉を聞くと、多くの人は「相手に何かしてあげる」という上下関係を感じるかもしれません。それだと配慮という言葉が、自立に矛盾するように感じることもあります。芥川賞受賞作「ハンチバック」の作者の市川さんは、「合理的配慮」を「合理的調整」にするべきだと提案しています。私も配慮という言葉より調整という言葉の方がしっくりくる気がします。
また、過去には障がいは個人の心身機能の障がいによるものと考えられていました。これを「医学モデル」と呼びます。しかし現在では、障がいは社会と心身機能の障がいが相まって作り出されるものであり、障害は社会にあるという「社会モデル」の考え方が主流です。
私は、社会に存在する障害を取り除くためには、人が「配慮」するのではなく、社会を「調整」することが重要だと考えています(配慮という言葉自体が悪いわけではありません)。「調整」に関しては、お互いに対話を重ね、共に解決策を検討することが重要です。そのためには、誰もが意見を述べることができる環境を整えることが必要だと思います。
これからも私たちが変わるだけではなく、社会そのものが変わり、誰一人取り残さない社会が形成されることを願っています。
ここで自分の趣味についてもお話したいと思います。
私は多趣味で広く浅いため、これといったものはありませんが、今のマイブームは筋トレです。筋トレはメリットしか存在しなく、運動して身体も健康になり、夜もぐっすり眠れます。また、テストステロンや、セロトニンなども分泌され、自信もついて良いことだらけです。是非皆さんも少しずつでも良いので身体を動かしましょう!



